1. はじめに
営業と聞くと「誠実さ」が第一に思い浮かぶかもしれません。しかし、実際の営業現場では、相手との関係性を築きながら、次の仕事につなげていく“したたかさ”や“狙い”も必要です。
今回は、私が福祉用具の現場で部下に指導している営業の考え方、そして“下心”という少し刺激的なキーワードの真意についてお話しします。
2. 下心=「先を読む力」と「見返りを想定する力」
「下心を持て」と言うと少し角が立つかもしれませんが、ここでいう下心とは、「このやりとりを通して、どう次につなげていくか」という戦略的思考のことです。
例えば、あるケアマネージャーさんが難しい案件を依頼してきたとします。これに対応することで、「この人は信頼できる」「また次もお願いしたい」と思ってもらえるかもしれません。しかし、相手によっては、ただ都合よく使われて終わるだけというケースもあります。
営業において大切なのは、「誰に」「何を」提供することで、「どのような見返り」があるかを読み取ることです。
3. ケアマネごとに戦略を変える
同じような依頼でも、ケアマネージャーさんによって対応を変える必要があります。
相手のタイプや反応を観察し、「この方は感謝の言葉や紹介で返してくれる方か」「単に便利だから依頼しているだけか」を見極める力が必要です。
- 関係構築が進んでいる相手には先回りした対応
- 結果が返ってこない相手には“線引き”も必要
こうした判断ができるようになると、営業の質が格段に上がります。
4. 行動にはすべて“意図”を持たせる
私が部下に必ず伝えているのは「行動には必ず目的を持て」ということです。
営業トークにも、ただの雑談のように見える中に「今後の関係性を深めるため」「紹介を得るため」といった意図を忍ばせることが大切です。
「この話をすることで、何を得たいのか」
「この対応の先に、どんな仕事が生まれるか」
こうした思考が、無駄な動きや浪費を減らし、効率的な営業活動につながります。
5. 下心を“思いやり”に変える
ここまで「下心」と表現してきましたが、これは言い換えれば“思いやり”でもあります。
「このケアマネさんは、こうしてくれたら助かるだろうな」「忙しそうだから先に情報を揃えて渡しておこう」
こうした配慮は、結局のところ相手のためになり、信頼と次の仕事を生む原動力になります。
6. まとめ
営業とは「関係性を築く力」と「戦略的に動く力」の両輪で成り立っています。
“下心”を持つというのは、決して悪いことではなく、「次の仕事を見据えた行動の裏付け」です。
ケアマネージャーや顧客とのやり取りの中で、相手ごとの対応を見極め、
効果的な営業活動を展開していくことが、これからの時代の営業に必要な姿勢ではないでしょうか。

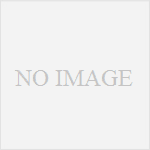

コメント