いつもご覧いただきありがとうございます。
今回は「福祉用具の貸与制度がどのように変化してきたか」について、現場目線でわかりやすくまとめてみたいと思います。
■ 介護保険制度が始まった頃はどうだったのか?
まず最初に押さえておきたいのは、介護保険制度のスタートは2000年(平成12年)4月。
それまでは家族による介護が基本でしたが、少子高齢化の進行を受けて、社会全体で支える仕組みとして介護保険が導入されました。
制度開始当初は、今よりも規制がゆるやかで、特に福祉用具の貸与においては自由度が高かったのが特徴です。
たとえば、要介護度が軽い人でも特殊寝台(電動ベッド)を借りられた時代。
利用者側が「これが必要」と思えば、比較的スムーズに借りられました。
■ 今の制度では何が変わったのか?
現在では、介護度に応じて貸与できる福祉用具が明確に制限されています。
※【補足:2024年現在の介護度別・貸与可能福祉用具例】
| 介護度区分 | 貸与できる主な福祉用具(例) |
|---|---|
| 要支援1・2・要介護1 | 手すり、歩行補助杖、スロープ、歩行器、歩行車など(軽度者向けの移動・動作補助用具) |
| 要介護2以上 | 特殊寝台(電動ベッド)、車いす、床ずれ防止用具など |
つまり、「好きな時に、好きなものを」借りられる時代は終わったのです。
■ 価格に関する最大の変化「上限価格制度」
近年の制度変更でも特に影響が大きかったのが、福祉用具に対する「上限価格」の導入です。
この制度は、各用具ごとに「これ以上の価格では貸与できない」という上限を定めたもの。
かつては、例えばベッド1台を月10万円で貸すような事例もありました(これは悪質なケースですが、現実に存在していました)。
そうした過剰請求を防ぐために上限が設定され、事業所が自由に価格を設定できる時代は終焉を迎えました。
■ 上限価格導入による影響と対応
この制度改正により、以下のような影響が現場に出ています:
- 売上が下がった事業所が多い
- 価格競争ができなくなったため、サービスや対応力で差別化する必要がある
- 利益率が圧縮され、「経営が成り立たない」として撤退する事業所も
実際に、筆者の地域でも福祉用具事業所の撤退が起きています。もともと少ない市場規模の中で、生き残るためには相当な工夫と戦略が必要です。
■ これから福祉用具事業を始める人・続ける人へ
今後の福祉用具事業では、以下の3点が特に重要になってくると感じています:
- 営業活動の強化
→ 自ら動き、ニーズを把握し、信頼関係を築くことが第一。 - 制度理解と価格設計の見直し
→ 上限価格の中でどう利益を出すか、仕組み作りが鍵。 - 事業継続のためのリスクヘッジ
→ 地域包括支援センターとの連携や、他サービスとの併用戦略も検討。
単に「良い福祉用具を提供する」だけではなく、制度の中でどうやって価値を届けるかが問われる時代になりました。
■ 最後に:制度は変わる。でも、想いは変わらない。
介護保険制度は、開始以来何度も見直し・改正を経て、現在の形に至っています。
そのたびに福祉用具の役割や位置づけも変わってきました。
ですが、私たちが「利用者さんに快適な生活を提供したい」という思いは、今も昔も変わりません。
制度に振り回されるのではなく、しっかりと理解し、時代に合った戦略で前に進むことが求められています。
これから事業を始める方も、今まさに運営している方も、この記事が一つの指針となれば幸いです。
🔍 制度の運用や価格設計でお悩みの方へ
「営業って何から始めたらいい?」「うちの価格設定は大丈夫?」など、事業運営に関するご相談も受け付けています。ぜひお気軽にどうぞ。
✅ 個別無料相談はこちら → https://forms.gle/htfpMeQVqAZDjPVD9
✅ LINEでのご相談はこちら → https://lin.ee/inTHLxh
(具体的な相談内容例:「制度改正に対応できていない」「営業先をどう広げたらいいかわからない」など)
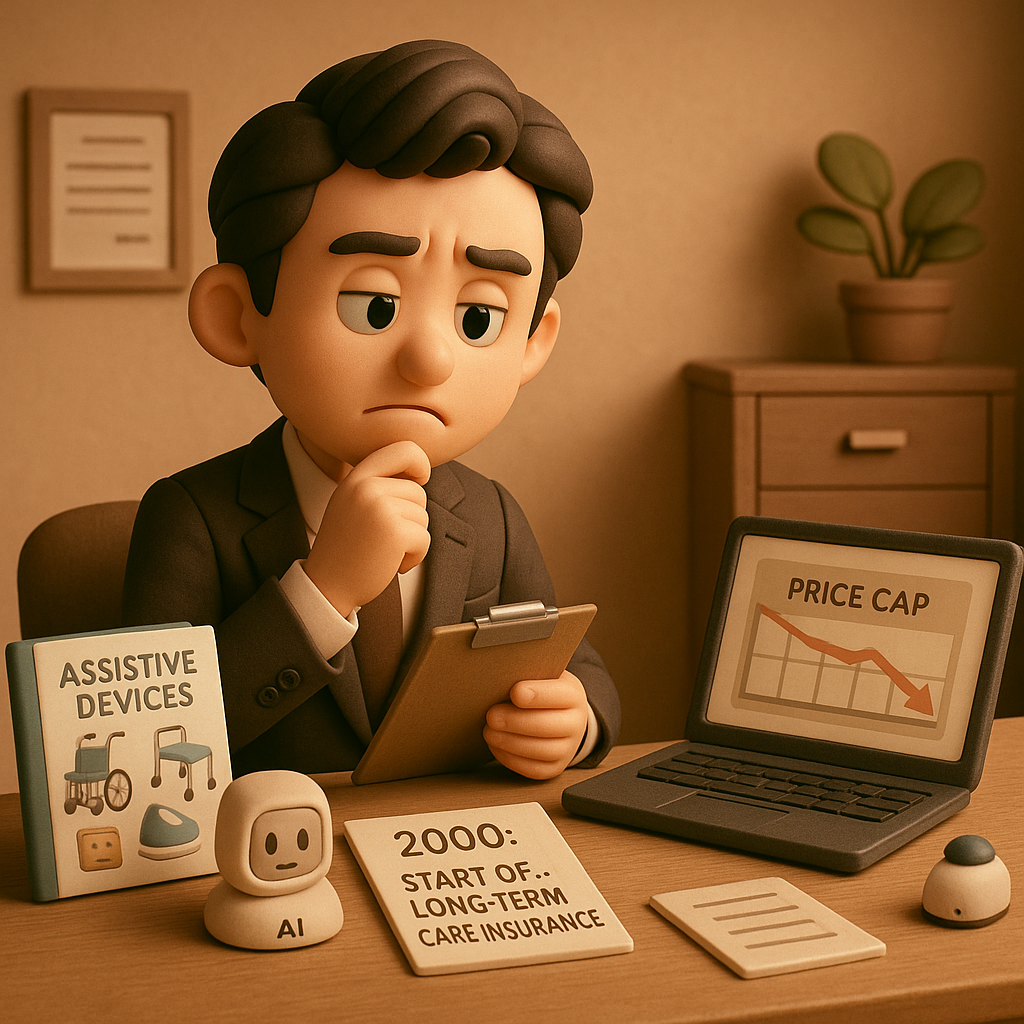
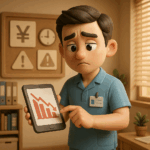

コメント