住宅型有料老人ホームにおいて、どのような外部サービスを導入するかは、経営者・管理者にとって非常に重要な判断ポイントです。
そのなかでも、意外と見落とされがちなのが**「薬剤師許諾療養管理指導」**という選択肢です。
医療系外部サービスの一例
施設に導入できる医療系の外部サービスには、以下のようなものがあります。
- 医師の許諾による療養管理指導
※主治医や訪問医が、定期的に施設を訪れ、病状の確認や生活指導を行うサービスです。 - 薬剤師の許諾による療養管理指導
※薬剤師が利用者の薬の内容や服薬状況、副作用の有無を確認し、必要に応じて処方医や施設職員と連携して指導・助言を行う訪問型サービスです。 - 訪問診療、訪問看護など
いずれも介護保険外サービスであり、利用者や家族と個別に契約を結ぶ必要があります。
なぜ「薬剤師指導」は重要なのか?
「うちの施設では入れていません」という話も珍しくないのが、この薬剤師による療養管理指導。
しかし、住宅型有料老人ホームのように医療対応に一定の柔軟性がある施設では、むしろ積極的に導入すべきサービスと言えます。
利用者負担が増えるという懸念
たしかに、薬剤師指導を導入すると、
利用者1名あたり月700円〜1000円程度の自己負担が発生します。
これを理由に導入を見送る施設もあります。
しかし、それによって施設側に重い負担がのしかかるケースがほとんどです。
薬の仕分けは、現場では非常に大きな業務負担
施設職員が薬の仕分けを担う場合、次のような問題が生じます:
- 朝・昼・夕・就寝前など、時間帯ごとの仕分けに手間がかかる
- 利用者ごとに異なる服薬内容を間違えずに管理するのは大きなプレッシャー
- 誤薬(ごやく:薬の飲み間違い)リスクが常につきまとう
- 看護師への過度な業務依頼が発生し、人材疲弊につながる
特に看護師のリソースが限られている施設では、これがフラストレーションや離職の原因になりかねません。
導入のメリットは「安全」と「時間」の確保
薬剤師指導を導入することで、以下のメリットが期待できます:
- 薬剤師が薬を管理するため、誤薬のリスクを低減できる
- 服薬内容の見直しや、飲み合わせの確認などの専門的支援が受けられる
- 職員の薬仕分け業務が不要になり、業務効率が大幅に向上する
- 看護師・介護職ともに本来の業務に集中できる環境が整う
これらの効果は、利用者満足度だけでなく、スタッフの働きやすさや職場の定着率にも直結します。
ご家族への説明と納得形成がカギ
もちろん、追加費用が発生することについては、利用者のご家族に対して丁寧な説明が必要です。
- なぜ導入するのか
- 誤薬リスクや職員の負担軽減という観点
- サービスの具体的な内容と実施頻度
- 月額の費用目安
これらを整理して共有することで、ご家族の理解と協力が得られやすくなります。
最後に:現場の「小さな改善」が未来をつくる
薬剤師指導の導入は、たしかに小さな一歩かもしれません。
しかし、職員のフラストレーションを軽減し、快適な職場環境を維持するための大きな鍵でもあります。
人手不足や業務過多が課題となる介護業界だからこそ、こういった部分への投資が、現場を守り、利用者の安全を守ることにつながるのです。
「うちの施設でも導入できるのか?」「説明時の工夫は?」など、具体的なご相談も承っています。以下からお気軽にご連絡ください。
✅ 個別無料相談はこちら → https://forms.gle/htfpMeQVqAZDjPVD9
✅ LINEでのご相談はこちら → https://lin.ee/inTHLxh

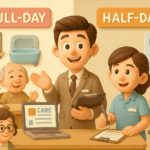

コメント