1. はじめに
介護保険サービスの提供において、モニタリングは重要な業務の一つとされています。特に福祉用具貸与の事業所では、ケアマネージャーからモニタリングの実施を依頼されたり、報告を求められる場面も多くあります。しかし、そのモニタリング、本当に意味があるのでしょうか?今回は、私が福祉用具事業所を運営してきた中で実際に感じたモニタリングの意義と、本当に求められている対応とは何かについてお話ししていきます。
2. 頻繁なモニタリングが引き起こすギャップ
福祉用具の事業を始めたばかりの頃、私は「お客様のためになる」と信じて、モニタリングを頻繁に実施していました。1ヶ月に1回、時には数週間に1度のペースで電話や訪問をして、福祉用具の使用状況や不満がないかを丁寧に聞き取っていました。
ところが、思った以上にお客様の反応は冷ややかでした。
- 「そんなに頻繁に電話されても困る」
- 「何かあればこっちから連絡します」
- 「特に問題ないので、大丈夫です」
など、こちらが”親切心”だと思って行っていたことが、かえってお客様のストレスになっていたこともありました。
3. モニタリングの本当の役割とは
この経験から私は気づきました。モニタリングの本質は「お客様にとって安心できる環境を整えること」であり、「形式的な確認作業」ではないのです。
電化製品の例で考えるとわかりやすいかもしれません。もしテレビや掃除機を買った後に、販売店から毎月「調子はいかがですか?」と連絡が来たら、正直ちょっと面倒に感じるかもしれませんよね。それと同じで、福祉用具でも必要以上に干渉されるのは望まれていないのです。
4. シフトチェンジ:対応力こそが信頼に繋がる
そこで私は発想を切り替えました。
モニタリングを「頻度」ではなく「質」で考えるようにしたのです。
- 定期的な電話連絡を減らす
- その代わりに、何かあったときの”即対応”を徹底する
この”即対応”を実現するには、以下のような工夫が必要です。
4-1. スケジュールを詰め込みすぎない
常に余裕のある予定管理を行い、急な対応依頼にもすぐに動ける体制をつくります。
4-2. 書類作成は事務所に戻ってから
日中は対応を最優先にし、書類作成などの事務作業は可能な限り夕方以降に回す。これにより緊急の要望にも素早く動けます。
5. お客様が本当に求めていること
モニタリングは「安心感を提供すること」が目的です。 それは形式的な確認作業ではなく、
- “必要なときに頼れる存在であること”
- “すぐに動いてくれるという信頼感”
これこそが、お客様が求めている本質だと思います。 実際、対応が早かったことで「ありがとう、助かったよ」と言われたことの方が、定期的なモニタリングよりもよほど信頼を得るきっかけになっています。
6. まとめ
モニタリングはもちろん大切な業務です。ただし、「やること」自体が目的になってしまってはいけません。
✅ お客様の負担にならない形で安心感を与えること ✅ 何かあったときの即対応体制を整えること ✅ スタッフ間での優先順位の共有と調整
これらを意識しながら運営していくことで、より良いサービス提供が可能になります。形式的な業務の継続ではなく、信頼される事業所になることを目指して、モニタリングの在り方を見直してみてはいかがでしょうか?
☑️ 今回の記事を読んで、さらに詳しく聞きたい方や、実際の対応事例を知りたい方はお気軽にご相談ください。
✉️ 個別のご相談はこちらから → Googleフォーム
📢 LINEで気軽に相談 → LINE公式アカウント


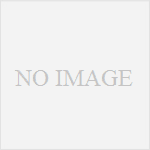
コメント