いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
今回は、介護施設を運営する中で意外と見落とされがちなテーマ、「入居者の紹介元の違い」について取り上げます。
入居者の多くは、何らかの“紹介”によって施設へやってきます。主なルートは2つ。
- ケアマネジャー(以下:ケアマネ)からの紹介
- 病院(主にソーシャルワーカー)からの紹介
どちらも重要な流入経路ですが、施設運営においてはそれぞれに明確な違いがあります。
ケアマネからの紹介|関係性は深いが制約も
まず、ケアマネからの紹介は、普段の事業所間のやりとりが土台にあるため、紹介されるケースが多いです。
訪問介護や通所介護などで連携している場合も多く、紹介をもらいやすい土壌があると言えます。
しかし、施設側から見ると以下のような“難しさ”もあるのが実情です。
- 紹介時点ですでにケアマネが決まっている
- 担当ケアマネが変更しづらい(紹介元の関係で)
- 意思疎通が取りにくいケアマネの場合、運営に支障が出る
「このケアマネさん、話が通じにくいな…」という場合でも、施設側からケアマネの交代を申し出るのは非常にハードルが高いです。
そのため、入居後の支援体制が不安定になったり、事業所として望ましい方向に進みにくくなったりすることがあります。
病院からの紹介|ケアマネ選定の自由度が高い
一方、病院(特にソーシャルワーカー)からの紹介では、ケアマネが未設定のケースが多いのが特徴です。
たとえば――
- 高齢者が急に入院
- 退院時に「自宅生活が困難」と判断される
- 病院側が施設入所を提案
- ソーシャルワーカーが紹介先を探す
- 介護保険未利用のため、ケアマネ不在
こういった背景があるため、施設側からケアマネを選定できる自由度があるという点が大きなメリットです。
自分たちと信頼関係のあるケアマネに依頼することで、以下のようなメリットが生まれます。
- 入居後の支援体制がスムーズ
- 情報共有や緊急対応のレスポンスが早い
- 継続的な関係性が築きやすく、紹介の連鎖も期待できる
結果として、施設の運営や経営の安定性にもつながっていきます。
紹介元の見極めは、施設経営のカギ
もちろん、ケアマネ紹介にも良さがありますし、病院紹介にも課題がないわけではありません。
例えば、病院側の紹介担当者(MSW)との関係性ができていなければ、継続的な紹介は難しくなります。
しかし、戦略的に見たとき、病院ルートの強化は非常に有効な手段になり得ます。
- ソーシャルワーカーとの信頼関係の構築
- 地域の急性期病院や回復期病院への訪問
- 退院支援カンファへの積極的な参加
こういったアクションを取ることで、病院紹介の流れを自施設に引き寄せることが可能です。
まとめ:紹介ルートは「数」より「質」で選ぶ
最後に強調したいのは、**紹介ルートの「数」より「質」**を重視すること。
どれだけ入居相談があっても、その後の支援体制が不安定では、施設運営は長続きしません。
- 「誰が入るか」と同じくらい「誰と支えるか」が重要
- 病院紹介ならケアマネ選定の自由度が高い
- 長期的な施設経営においても戦略的に優位になる
そんな視点から、改めて自施設の紹介体制を見直してみてはいかがでしょうか。
「うちの地域では病院連携が弱くて…」「どこからアプローチすべきか悩んでいる」など、
具体的なご相談や状況のヒアリングも可能です。お気軽にお声かけください。
✅ 個別無料相談はこちら → https://forms.gle/htfpMeQVqAZDjPVD9
✅ LINEでのご相談はこちら → https://lin.ee/inTHLxh
(例:「病院とのつながりを作るには何から始める?」といったご相談もOKです)

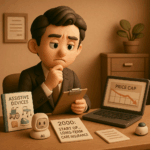
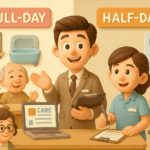
コメント